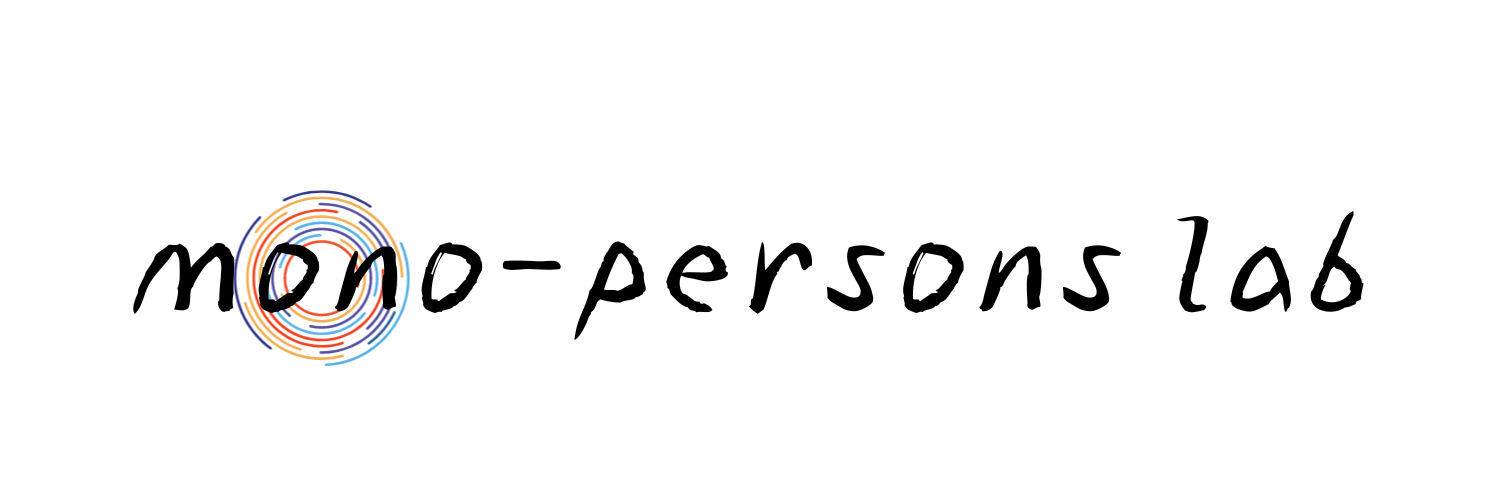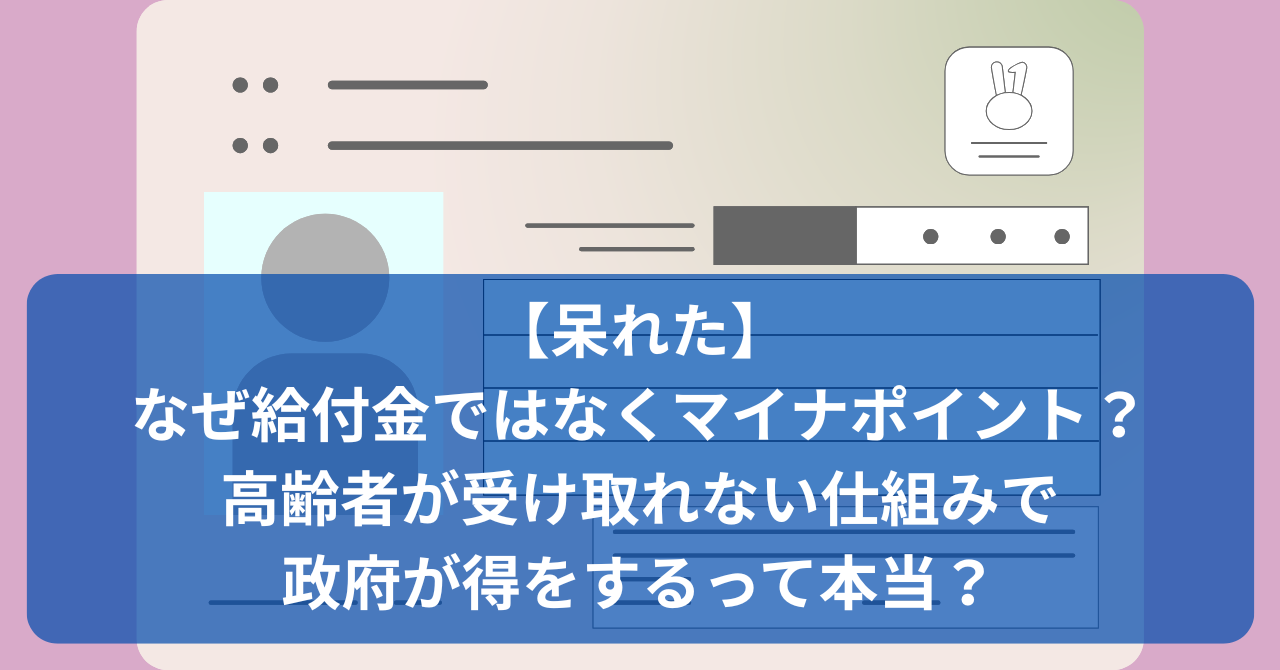「なんでマイナポイントなの?」「公金受取口座、あれ結局なんだったの?」
最近の報道で浮上している“マイナポイントによる支援策”に対し、SNSでも不満の声が続出しています。
特に、高齢者やスマホを使えない人にとっては「申請制」の時点でハードルが高く、
「わざと受け取れない仕組みにしてるのでは?」という疑念すら浮かんでいる状況です。
この記事では、なぜ政府が再びマイナポイント方式を検討しているのか、
そして給付金と比較して何がどう違うのかを、制度の仕組みやネットの声を交えてわかりやすく解説します。
なぜ「給付金」ではなく「マイナポイント」が再び浮上?その理由と背景をわかりやすく解説

2025年4月、政府がまたもや「マイナポイント支給」の検討に入ったという報道が出てきました。
物価高が続く中で、多くの人が期待していたのは“現金での給付金”。
それなのに、なぜまたポイント方式なの?と不満や疑問が噴出しています。
この章では、そもそもマイナポイントとは何か、なぜ現金じゃないのか…その背景を紐解いていきます。
ちなみに、現金支給の給付金と減税のどちらが良いのか?という点も、SNS上で大きな話題になっています。
→【徹底比較】減税と給付金どっちがいい!?SNSでは8割が減税との結果!
マイナポイントは何が狙い?給付金とは違う“使わせる支援”の仕組み
マイナポイントは、マイナンバーカードとキャッシュレス決済をひも付けることで、一定額のポイントがもらえる制度。
これまでにも「カード取得」「保険証登録」などの条件でポイントが支給されてきました。
政府側の狙いは、「使ってもらう支援=経済を回す支援」。給付金は貯金に回ってしまうケースも多いので、それよりは消費を促進したいというわけです。
なぜ現金で配らないの?申請制+ポイント還元にした本当の理由とは
給付金だと“全員に自動で支給”する必要があるため、国の財政負担が重くなります。対してマイナポイントは「申請した人にだけ支給」という仕組みなので、結果的に受け取る人数が絞られ、コストも下がります。
加えて、決済サービス会社などに事務手続きを委託することで、政府側は手間を抑えつつ支援の実績を作ることができる。つまり、“選ばれた人だけが得をする”構造になっているわけです。
高齢者やデジタル弱者はどうなる?公金受取口座と“もらえない仕組み”への疑問
マイナポイント方式の支援が再浮上したことで、以前登録が義務づけられていた「公金受取口座」は一体何だったのか?という声も出ています。
また、高齢者などスマホを使えない層が“申請できずにもらえない”という状況は、見方によっては「政府がわざと取りこぼしを狙ってるのでは?」という疑念にもつながっています。
「口座登録したのに意味なかった?」公金受取口座と給付金のすれ違い
2023年頃に大々的に進められた「公金受取口座の登録」。
多くの人が「今後の給付金の自動振込のため」と理解して登録したにも関わらず、今回の支援案ではその仕組みは一切使われていません。
登録させるだけさせておいて、実際の支給には使わないとなれば、「結局、国に都合のいい情報収集だったのでは?」と不信感を抱かれても仕方ありません。
「申請しなきゃもらえない=自己責任?」高齢者やジジババ外し説は本当か
今回のマイナポイント案が物議を醸している理由のひとつが、「申請できない人=受け取れない人」という構図です。
特にスマホを持っていない高齢者や、マイナンバー関連の手続きが苦手な人にとっては、事実上“支給対象外”になってしまう現実があります。
「申請しなかったのが悪い」とされれば、支援から外れても誰も責任を取らない構造に…。ネット上でも「ジジババ外しでは?」という声が多く見られます。