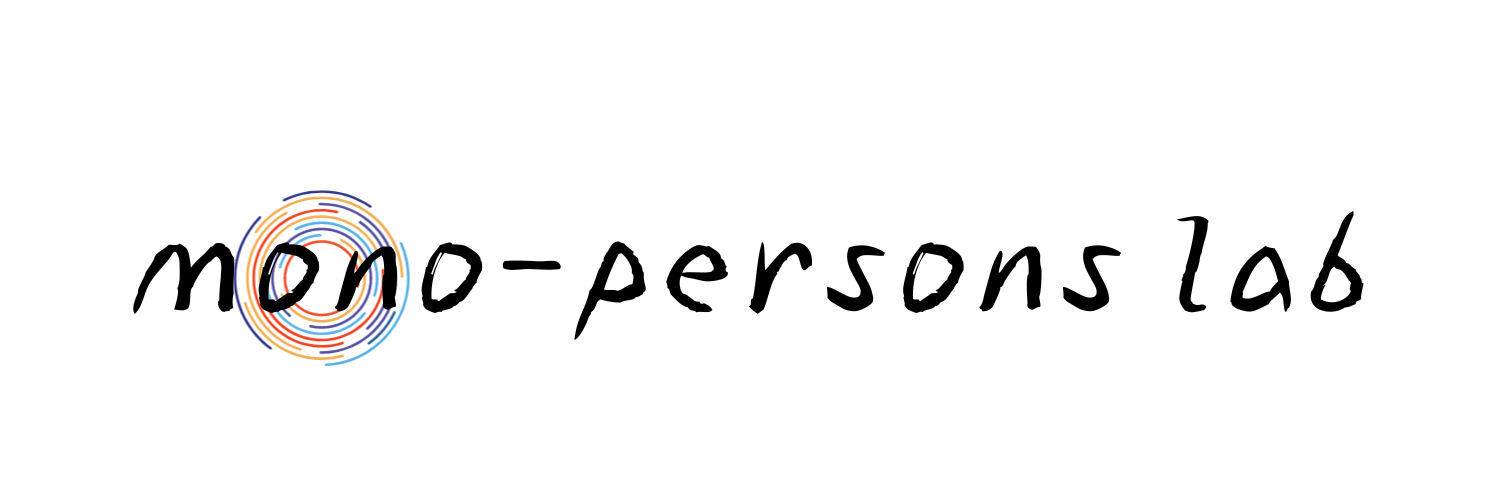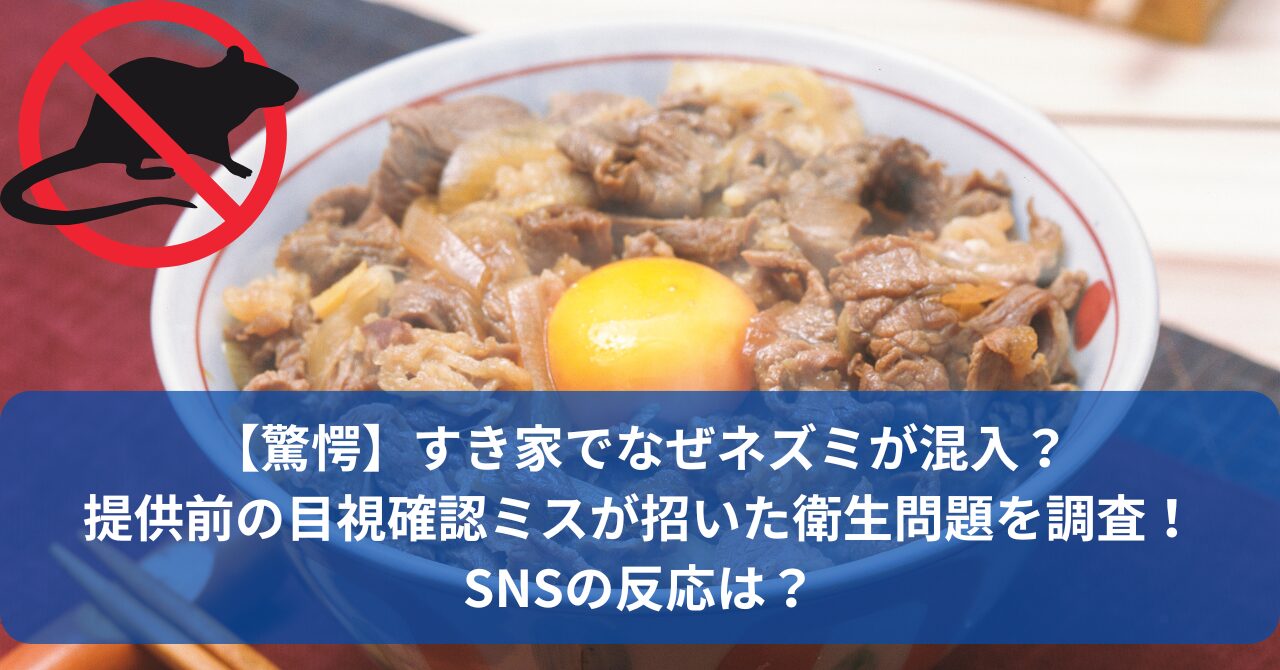2025年1月、すき家の鳥取南吉方店で提供されたみそ汁にネズミの死骸が混入していたことが発覚し、SNSを中心に大きな話題となりました。
この事件はGoogleレビューへの投稿をきっかけに拡散され、「なぜこんなことが起こったのか?」という疑問が広がりました。
すき家は公式サイトで異物混入の事実を認め、提供前の目視確認を怠ったことが原因であると説明しています。
しかし、問題はそれだけではありません。
建物の衛生管理体制や害獣侵入対策の不備、さらには約2ヶ月間公表を控えていた企業の対応にも厳しい目が向けられています。
本記事では、すき家のネズミ混入事件について、発生の経緯や原因、衛生管理の実態、そしてSNSでの反応まで詳しく解説します。
- すき家でネズミ混入事件が発生しSNSで拡散
- 原因は提供前の目視確認ミスと衛生管理の不備
- すき家は全国の店舗で衛生対策強化を発表
- SNSでは不買運動の声もあり、ブランドイメージに影響
すき家でなぜネズミがみそ汁に混入してしまったのか?
2025年1月、すき家の鳥取南吉方店で提供されたみそ汁にネズミの死骸が混入していたことが発覚しました。
この事件はGoogleレビューに投稿された写真をきっかけにSNSで拡散され、大きな波紋を呼びました。
異物混入の原因は、調理段階での管理不足や提供前のチェックが行われなかったことにあります。
本章では、ネズミがどのように混入したのか、その経緯とすき家の管理体制の問題点を詳しく解説します。
混入の原因とそのメカニズム
すき家の発表によると、ネズミはみそ汁の具材をお椀に入れて準備する過程で混入した可能性が高いとされています。
一般的に、飲食店では調理場の衛生管理を徹底し、異物混入を防ぐための設備を整えていますが、今回の事例ではそれが機能しなかったと考えられます。
調査の結果、店舗の構造上の問題(建物のクラックや隙間)により、ネズミが侵入しやすい環境だったことも判明しました。
このような状況が整ってしまうと、食材の保管や調理過程で異物が混入するリスクが高まります。
提供前の目視確認はなぜ行われなかったのか?
すき家は公式声明の中で、「提供前の目視確認を怠った」と明言しています。
通常、飲食店では提供直前に商品の状態を確認するルールが設けられていますが、今回はその確認作業が徹底されていなかったため、異物の混入に気づかず提供されてしまいました。
忙しい時間帯だった可能性もありますが、それでも提供前のチェックを省略することは飲食業において重大なミスと言えます。
この事態を受け、すき家は全国の店舗に対し、提供前の目視確認を改めて徹底するよう指示を出しました。
すき家のネズミ混入について衛生管理体制と問題点

今回のネズミ混入事件は、単なるヒューマンエラーにとどまらず、すき家の衛生管理体制そのものに課題があったことを浮き彫りにしました。
すき家は全国に2,000店舗以上を展開しており、各店舗で衛生基準が適切に運用されているかが重要なポイントとなります。
本章では、すき家の通常の衛生管理ルールと、問題のあった店舗の実態について掘り下げます。
すき家の通常の衛生管理ルールとは?
すき家では、食品の安全を確保するためにいくつかの衛生管理ルールを設けています。
| 管理項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 店舗の清掃・消毒 | 開店前・閉店後の清掃、調理器具の洗浄・消毒、アルコール消毒の実施 |
| 食材の管理 | 冷蔵・冷凍庫の温度管理、消費期限の厳守、入荷時の品質チェック |
| 害虫・害獣対策 | 建物のひび割れ点検、防虫・防鼠設備の設置、ゴミの適切な管理 |
| 従業員の衛生管理 | 手洗い・消毒の徹底、手袋・マスクの着用、体調不良時の勤務制限 |
| 提供前のチェック | 料理提供時の目視確認、ダブルチェック体制の導入 |
| 外部監査 | 保健所・衛生機関の定期監査、指摘事項の即時改善 |
一般的には、店舗ごとに衛生チェックリストが用意され、開店前や閉店後に定期的な清掃が行われています。
また、食材の管理においても、一定の温度管理や密閉容器の使用など、異物混入を防ぐための基本ルールが存在します。
さらに、従業員には定期的な衛生研修が実施されており、食品の取り扱いに関する指導が行われているはずです。
しかし、これらのルールが徹底されていなかった可能性があります。
問題の店舗における衛生管理の実態
すき家の発表によれば、今回の事件が発生した店舗では、建物のクラック(ひび割れ)や隙間があり、そこからネズミが侵入していたことが分かりました。
また、日常的な衛生管理が不十分だった可能性も指摘されています。
通常であれば、害獣の侵入を防ぐために定期的な点検を行い、問題があればすぐに補修する必要がありますが、その対策が適切に実施されていなかったことが、今回の混入につながったと考えられます。
すき家はこの問題を受け、四半期ごとの建物点検を義務付け、異物混入を防ぐための管理体制を強化すると発表しました。
すき家のネズミ混入についてSNSでの反応は?
この事件は、SNSを通じて瞬く間に拡散され、多くの人々の間で話題になりました。
特に、視覚的に強烈なインパクトを持つ画像が広まったことで、消費者の不安が一気に高まりました。
ここでは、SNSでの反応と、すき家のブランドに与えた影響について詳しく見ていきます。
XやInstagramで拡散された投稿
事件発覚のきっかけとなったのは、Googleレビューに投稿された写真ですが、その後X(旧Twitter)やInstagramでも急速に拡散されました。
「こんなものを提供するなんて信じられない」「もう二度と行かない」といった怒りの声が多数見られました。
一方で、「AIによるフェイク画像では?」という疑念の声もあり、真偽をめぐる議論も展開されました。
しかし、すき家が公式にネズミ混入を認めたことで、消費者の不安はさらに高まりました。
「もう行かない」?炎上によるすき家への影響
この騒動によって、すき家のブランドイメージは大きく損なわれました。
Xでは「#すき家不買運動」というハッシュタグが登場し、一部の消費者がすき家の利用を控える動きも見られました。
また、他の飲食チェーンと比較される形で「松屋や吉野家は大丈夫なのか?」という疑問の声も上がりました。
すき家は対応策として、全店舗での衛生管理の徹底を発表しましたが、消費者の信頼回復には時間がかかる可能性があります。